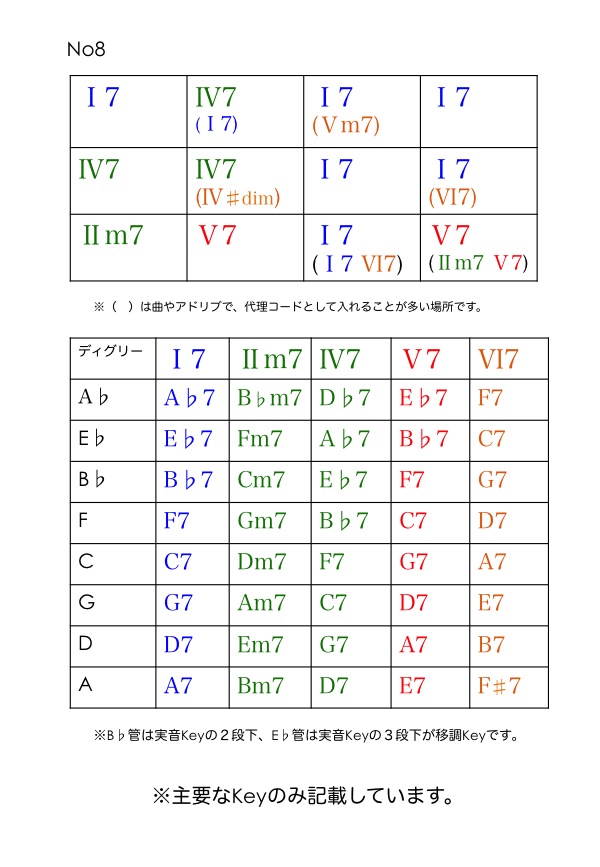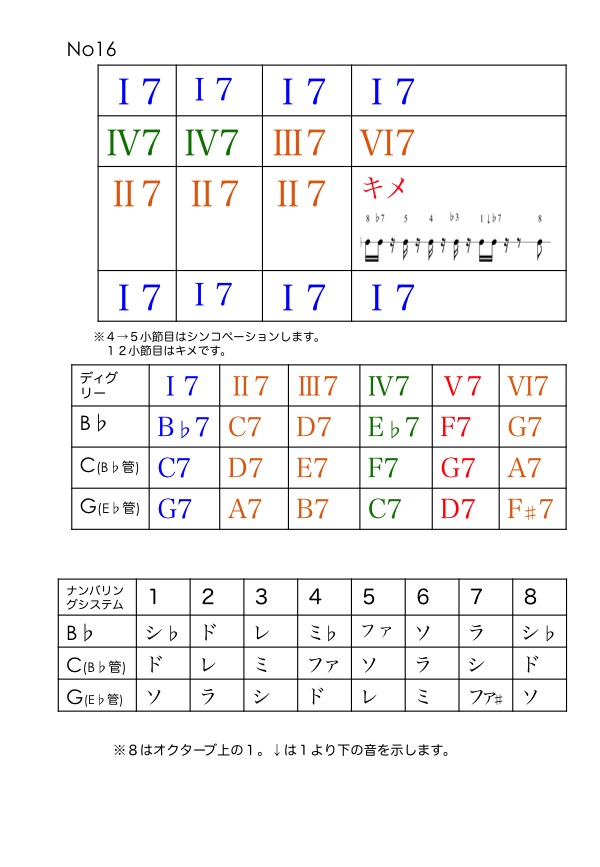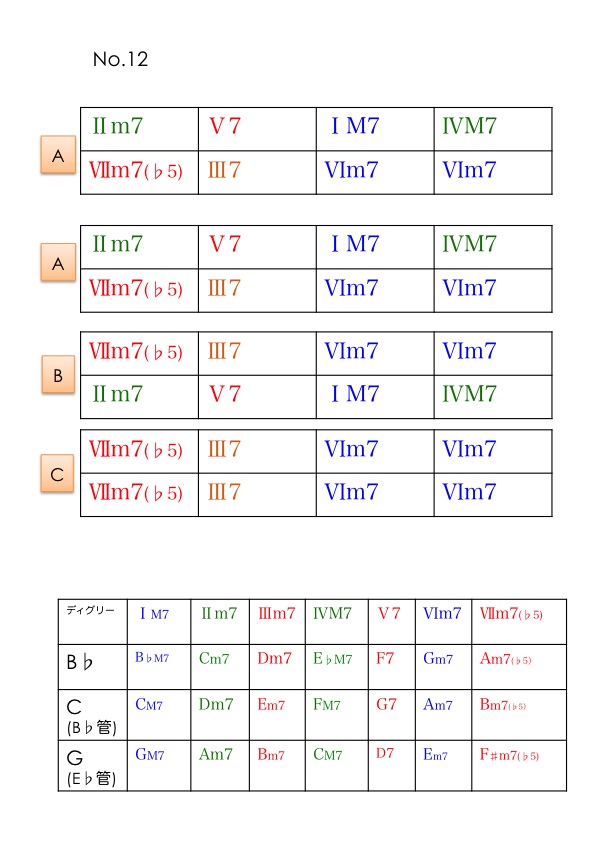(コード進行は一番下に掲載してあります。)
↓連続再生
個別の解説はこちら!
その1 セブンスコードを2音で表現
https://www.youtube.com/watch?v=PAsDwKgf7hk
解説はこちら
ジャズブルースは、その名の通り
ブルースとほぼ同じコード進行なので、
アドリブソロもブルースと同じように
取ることができます。
なので、
思いっきりブルージーに弾いても
大丈夫!ではあるのですが、
コードに沿った形の、
ジャズらしいアドリブを覚えると
ソロのバリエーションが広がります。
また、コードを意識して演奏すると
ロストしにくくなるという利点も
ありますから、
『コードに沿ってソロをとる』
という発想をぜひ身に付けてくださいね。
────では、
『コードに沿ってソロをとる』
とはどういうことなのか、
動画の内容を補足する形で
具体的に解説していきますね。
※今回の解説は
「ナンバリングシステム」を
理解しているものとして進めます。
ナンバリングシステムをまだ
学んでいない方は、
↓こちらの動画↓を先にご覧くださいね。
■キーFのジャズブルース
コード進行おさらい
|
F7
|
B♭7
|
F7
|
F7
|
|
B♭7
|
B♭7
|
F7
|
D7
|
|
Gm7
|
C7
|
F7
|
C7
|
『コードに沿ってソロをとる』とは、
ひとことで言ってしまえば
コードの構成音(コードトーン)を弾く
ということです。
これだけの話ですが、
言われていきなりできる人は
そうそういません。(^ ^;
「えーと、B♭7の構成音は
B♭、D、F、Aだから、
今はDの音を弾いておいて、
次はF7だから…」
───みたいなことを
コードが変わるごとに、
リアルタイムで考えながら演奏するのは
初心者にとってかなり難しいです。
そこで、まずは
アドリブで使う音を、
コードトーンのなかで
一番特徴的な音に絞ります。
F7のコードの場合は、1と♭7の音。
B♭7の場合は、1と♭3の音。
1の音を中心にフレージングしますが、
コードに合わせて♭3と♭7の
どちらを使うか選ぶ
という頭の使い方をします。
動画のなかでは、下記のような
かんたんなコード進行で
練習しています。
F7 – B♭7 – F7 – F7
B♭7 – B♭7 – F7 – F7
※青字の箇所は♭7、
緑字の箇所は♭3を弾きます。
動画の内容を参考にしながら、
「コードに合わせた音の使い分け」
を練習してみてくださいね!
その2 ツーファイブを1音で表現
https://www.youtube.com/watch?v=tohPHeBMGRI
https://www.youtube.com/watch?v=tohPHeBMGRI
解説はこちら
『コードに沿ってソロをとる』とは、
ひとことで言ってしまえば
コードの構成音(コードトーン)を弾く
ということです。
これだけの話なので、
一見すると簡単そうなのですが、
実際の演奏はリアルタイムで
どんどん先へ進んでいく中で、
狙った音を弾くというのは
慣れていないと、結構大変です。
そこで、
まずは弾く音を
1〜2音に絞って
練習していきます。
※この動画シリーズでは、
「ナンバリングシステム」を
理解しているものとして
解説を進めています。
■キーFのジャズブルース
コード進行おさらい
|
F7
|
B♭7
|
F7
|
F7
|
|
B♭7
|
B♭7
|
F7
|
D7
|
|
Gm7
|
C7
|
F7
|
C7
|
今回の動画で解説しているのは、
8小節目、9小節目、10小節目で
何の音を使うか?というポイントです。
前回のF7, B♭7と同様に、
各コードの構成音のなかで、
特徴的な1〜2音にだけ
使う音を絞り込みます。
8小節目のD7では「♭2」の音を、
9小節目のGm7と10小節目のC7では
「4」の音をそれぞれ弾くと、
1音だけでも「コード感」が表現できます。
動画の内容を参考にしながら、
「1音でコード感を出すソロ」
を練習してみてくださいね!
その3 1と2を合わせて1コーラス
解説はこちら
シリーズ1本目の動画では、
Fブルースのコード進行の
前半について、
2本目の動画では後半について
それぞれソロの取り方を
解説しました。
3本目の動画解説である今回は、
その2つをつなげて
1コーラス分のソロを
完成させる
のがテーマになります。
この動画シリーズでは、
コードごとに、使う音を
1〜2音に絞ってソロを取る
という方法で練習しています。
なぜこの方法をとるのかといえば、
アタマの使い方を練習する
ためです。
実際の「コードに沿ったソロ」は、
もっと使う音が多く、
フレーズも複雑です。
ごくごく一部の超天才を除いて、
アドリブ初心者には
絶対に真似できません。
そこで、まずはフレーズを簡単にして
「アタマの使い方」、つまり
どういう意識でソロを取っているか?
という点だけを真似ていくのです。
では、実際に練習していきましょう。
わかりやすく、コード進行の表に
各コードで使う音を書き込んでいくと、
こう↓↓なります。
|
F7
1,♭7
|
B♭7
1,♭3
|
F7
1,♭7
|
F7
1,♭7
|
|
B♭7
1,♭3
|
B♭7
1,♭3
|
F7
1,♭7
|
D7
♭2
|
|
Gm7
4
|
C7
4
|
F7
1,♭7
|
C7
4
|
念のため、ナンバリングと実音を
対応させて書いておきますね。
1 =F
♭2=G♭
♭3=A♭
4 =B♭
♭7=E♭
※この動画シリーズでは、
「ナンバリングシステム」を
理解しているものとして
解説を進めています。
この練習のポイントは、
コードが変わってから
使う音を切り替えるのではなく、
あらかじめ先のコードを予測して
使う音を狙っておくのです。
F7のコードのときに1と♭7を使って
フレージングをしながら、
アタマの中では「次は1と♭3…」と
意識して、次のコードに変わったときの
準備をしておくのです。
こういうアタマの使い方に慣れてくると、
ある音とある音をなめらかにつないで
綺麗なメロディを即興でつくる
ことができるようになってきます。
補助輪なしで自転車に乗れるようになるまで
時間がかかるのと同じように、
この練習も最初の頃は大変です。
しかし、この練習方法なら
確実にアドリブが上達していきますから、
音数を絞って練習しながら、
少しずつ慣れていってくださいね。
その4 ツーファイブをアルペジオ2音で表現
解説はこちら
前回までの動画解説で、
「音数を絞ったコードに沿ったソロ」
の1コーラス分の解説が終わりました。
動画を見ながらチャレンジしてみましたか?
※前回の動画はこちら
まだ難しくて上手くできないという方は、
1コーラスの全コードで
使う音を決めるのではなく、
5〜6小節目だけ、あるいは
9〜10小節目だけなど、
一部分だけ使う音を決めるようにして
この「アタマの使い方」に
少しずつ慣れていってくださいね。
さて。
今回は何をするのかといえば、
内容を少しレベルアップさせます。
【ツーファイブをアルペジオ2音で表現】
コード感を出すため、
各コードごとに
指定した音を弾く
という考え方は同じですが、
今回は音数を少し増やします。
8小節目のD7は♭2と3、
9小節目のGm7では4と2、
10小節目と12小節目の
C7では4と2、というように
全てのコードを2音で
演奏していきます。
前回同様、
コード進行表に使う音を
記入しておきます。
※黄色でハイライトしているのが
使う音が増えた箇所です。
|
F7
1,♭7
|
B♭7
1,♭3
|
F7
1,♭7
|
F7
1,♭7
|
|
B♭7
1,♭3
|
B♭7
1,♭3
|
F7
1,♭7
|
D7
♭2,3
|
|
Gm7
4,2
|
C7
4,2
|
F7
1,♭7
|
C7
4,2
|
念のため、ナンバリングと実音を
対応させて書いておきますね。
1=F
♭2=G♭
2=G
♭3=A♭
3=A
4=B♭
♭7=E♭
※この動画シリーズでは、
「ナンバリングシステム」を
理解しているものとして
解説を進めています。
ナンバリングシステムをまだ
学んでいない方は、
↓こちらの動画↓を先にご覧くださいね。
前回もお伝えしましたが、
この演奏でのポイントは、
コードが変わってから
使う音を切り替えるのではなく、
あらかじめ先のコードを予測して
使う音を狙っておくのです。
F7のコードのときに1と♭7を使って
フレージングをしながら、
アタマの中では「次は1と♭3…」と
次のコードに変わったときの
準備をしておくのです。
こういうアタマの使い方に慣れてくると、
ある音とある音をなめらかにつないで
綺麗なメロディを即興でつくる
ことができるようになってきます。
ほかにも、
ロストしにくくなる等、
セッション的に良い効果が
たくさん得られますので、
少しずつ慣れていってくださいね!
その5 ツーファイブをアルペジオ3音で表現
解説はこちら
今回は何をするのかといえば、
内容をさらにレベルアップさせます。
【1コーラスをアルペジオ3音で表現】
コード感を出すため、
各コードごとに
指定した音を弾く
という考え方は同じですが、
今回はコード1つにつき3音です。
けっこうレベルが上がってきました。
前回同様、
コード進行表に使う音を
記入しておきます。
|
F7
1,♭7,5
|
B♭7
1,♭3,6
|
F7
1,♭7,5
|
F7
1,♭7,5
|
|
B♭7
1,♭3,6
|
B♭7
1,♭3,6
|
F7
1,♭7,5
|
D7
♭2,3,5
|
|
Gm7
4,2,6
|
C7
4,2,5
|
F7
1,♭7,5
|
C7
4,2,5
|
念のため、ナンバリングと実音を
対応させて書いておきますね。
1=F
♭2=G♭
2=G
♭3=A♭
3=A
4=B♭
5=C
6=D
♭7=E♭
※この動画シリーズでは、
「ナンバリングシステム」を
理解しているものとして
解説を進めています。
ナンバリングシステムをまだ
学んでいない方は、
↓こちらの動画↓を先にご覧くださいね。
これは、
アドリブでそのまま使うというより
「練習」の意味合いが強いです。
この練習の目的は、
「演奏している今この瞬間」ではなく、
次の小節、4小節先、あるいは8小節先へ
意識を向けながら演奏することに慣れる、
ということです。
こういうアタマの使い方に慣れてくると、
ある音とある音をなめらかにつないで
綺麗なメロディを即興でつくる
ことができるようになってきます。
ほかにも、
ロストしにくくなる等、
セッション的に良い効果が
たくさん得られます。
今回の内容が難しいと感じる方は、
いきなり3音のアルペジオに
チャレンジするのではなく、
もっと音数を絞ったところから
少しずつ慣れていってくださいね!
その6 ブルーススケール1発で1コーラス
解説はこちら
前回までの解説は、
「コードに沿ってソロをとる」
というやり方でした。
この方法を、音楽用語では
「コーダル」といいます。
一方、アドリブソロの取り方には
もうひとつ「モーダル」という
考え方があります。
これは、
コード進行にとらわれず、
スケールを中心に考えて
ソロをとる方法です。
「スケール一発」という言い方もします。
”スケール中心”に弾くとは、
具体的に言えば
何か弾いたらドに戻る
というやり方です。
※メジャースケールや
ペンタトニックスケールの
歌わせ方で解説しています。
モーダルな歌い方のほうが、
鼻歌でつくるような自然なメロディに
近いソロがとれるのですが、
コード進行と無関係に演奏するので、
どんな曲を弾いても
同じようなアドリブソロに
なってしまいがちです。
要するに、
スケール一発の発想だけでは、
マンネリするのです。
^^;
そのため、
「コードに沿ったソロ」のように
違った発想で考えることが
必要になるのですね。
この動画シリーズ、
ジャズブルース解説の後半は、
スケール一発のモーダルなソロに
少しずつコーダルの発想を混ぜていく、
という内容になっています。
まずは、モーダルにソロをとると
どんな印象になるのか、
動画でチェックしてくださいね!
【ブルーススケール1発で1コーラス】
その7 ブルース1発+ツーファイブアルペジオ
解説はこちら
前回は、コード進行にとらわれず
「スケール一発」でソロをとる、
という内容でしたが、今回からは
これに「コードに沿ったソロ」の
考え方を少しずつ混ぜていきます。
ブルース的な「モーダル」の発想と
ジャズ的な「コーダル」の発想の
ハイブリッドで、
ソロをとることを目指します。
言い方を変えると、
基本的には
スケール一発でソロをとるが、
一部分だけコード進行に沿って
アドリブをする
ということです。
では、ジャズブルースの場合に、
コードに沿ってソロをとる「一部分」は
どこにするのがよいでしょうか。
答えは「ツーファイブ」のところ。
9小節目と10小節目ですね。
ジャズブルースのなかで、
ジャズっぽさを担当しているのが
このツーファイブの部分です。
今回の動画シリーズでは
キーFで演奏していますので、
Ⅱm7-Ⅴ7は実音で書くと
Gm7-C7となります。
※何のことかさっぱり分からない…
という方は、まずは
「ディグリー」について解説した
こちらの動画を御覧くださいね。
ツーファイブと呼ばれるコード進行は
ジャズでよく使われるもので、
これが入っているだけで、不思議と
ジャズっぽく聞こえてくるのです。
ですから、
全体としてはスケール一発でも、
このツーファイブの部分では
しっかりと「コード感」を出すと、
ソロの響きもジャズらしくなります。
”コード感の出し方”は
このシリーズ前半で解説してきた、
コードに合わせて特定の音を弾く、
というやり方です。
コード進行に使う音を書き込むと、
こんな↓↓具合になります。
|
F7
指定なし
|
B♭7
指定なし
|
F7
指定なし
|
F7
指定なし
|
|
B♭7
指定なし
|
B♭7
(Bdim) 指定なし
|
F7
指定なし
|
D7
指定なし
|
|
Gm7
4, 2, 6
|
C7
4, 2, 5
|
F7
指定なし
|
C7
指定なし
|
このときのポイントは、
余裕をもってコードを狙う
ということ。
9小節目に入ってから
「えーと、今弾く音は…」
と考えるのではなく、
「あと2小節先にツーファイブがあるから
今のうちに準備しておこう」
といったように、
意識を先へ先へと持っていくのですね。
レッスン動画、あるいは
適当なカラオケ音源に合わせて
演奏をしながら、
演奏をしながら、
意識の向け方、「コードを狙う」感覚を
練習してみてくださいね!
その8 ブルース1発+ツーファイブフレーズ
解説はこちら
ジャズブルースの
「ジャズ」っぽさは
ツーファイブの部分です
と前回お伝えしました。
具体的にどこかといえば、
9〜10小節の Gm7 − C7と進むところですね。
■Fブルースのコード進行
|
F7
|
B♭7
|
F7
|
F7
|
|
B♭7
|
B♭7
|
F7
|
D7
|
|
Gm7
ツー
|
C7
ファイブ
|
F7
|
C7
|
前回は、このツーファイブのところで
2〜3音のアルペジオで演奏しましょう、
という内容でした。
今回は、
よりジャズらしく演奏するため、
ここにジャズの「お決まりフレーズ」
を入れます。
バップフレーズ とか、
オルタード系のフレーズ とか、
そんな名前で呼んでいるフレーズです。
ジャズでよく出てくるフレーズなので、
これを弾くとジャズっぽく聞こえます。
ピンとこない方は、
まず今回のレッスン動画を
ごらんになってください。
「あー、9〜10小節目で
何かやってるなー」
ということがわかれば、
まずはOKです。
【ブルース1発+ツーファイブフレーズ】
このツーファイブのところで
演奏するとよいフレーズは、
何種類かあります。
FTJS!のサイト内にも
動画がありますので、
個別にチェックしてみてくださいね。
○ツーファイブ進行について
○簡単オルタード3度解決
○簡単オルタード5度解決
○Ⅴ7のビバップフレーズ(はさみ型)
○Ⅱmのビバップフレーズ
───この辺りまで来ると、
かなり高度な内容ですので、
アドリブ初心者の方にとっては
ハードルが高いはずです。
今回の動画シリーズでは
回を追うのに合わせて
徐々にレベルを上げていく、
という内容になっています。
今日の内容が難しいなと感じたら、
これまでの内容を復習しつつ、
今の自分に合わせたレベルから
挑戦していってくださいね!
その9 ブルース1発+セカンダリードミナント&ツーファイブフレーズ
解説はこちら
まずは、
Fブルースのコード進行を
おさらいしておきましょう。
■Fブルースのコード進行
|
F7
|
B♭7
|
F7
|
F7
|
|
B♭7
|
B♭7
|
F7
|
D7
セカンダリー
ドミナント
|
|
Gm7
ツー
|
C7
ファイブ
|
F7
|
C7
|
前回は、
Gm7-C7のツーファイブで
ジャズのお決まりフレーズを
演奏しましょう
とお伝えしました。
ジャズブルースの9〜10小節目は
一番の盛り上がりどころ。
ここでしっかりばっちり
ジャズフレーズを決めると、
ソロ全体がジャジーに仕上がります。
このGm7-C7のところで
ツーファイブのフレーズを
しっかり決められるようになったら、
次にチャレンジすることは
8小節目のD7を意識することです。
このD7は、専門用語では
セカンダリードミナント
と呼ばれます。
難しい理論的な話を脇に置いて、
どう解釈すれば良いか?
だけをシンプルにお伝えすると、
ツーファイブに向かう
盛り上がりを演出している!
と捉えればOKです。
コードには
落ち着きと盛り上がりしかない、
というシンプルな捉え方に基づけば、
セカンダリードミナントは
盛り上がりコードです。
通常の盛り上がりコードは、
落ち着きコードに向かって
解決(着地)するのですが、
セカンダリードミナントは
次の盛り上がりコードに向かって
(落ち着かずに)進んでいきます。
そして、今回の場合は
セカンダリードミナントが向かう先が
ジャズらしいツーファイブの
盛り上がりコードですから、
このD7のセカンダリードミナントでも
ジャズのお決まりフレーズを
うまく決められると、
さらにジャジーな雰囲気で
ソロを盛り上げることができます。
もう少し具体的にいえば、
D7は、Gから見るとⅤ7になりますから、
「D7からGm7へ解決する」と捉えると
Ⅴ7のフレーズが綺麗にはまります。
やはり難易度は高くなりますが、
ツーファイブだけでなく、
このD7まで含めて、
このD7まで含めて、
ジャズフレーズを決められるように
チャレンジしてみてくださいね!
■Ⅴ7のフレーズ例
○簡単オルタード3度解決
○簡単オルタード5度解決
○Ⅴ7のビバップフレーズ(はさみ型)
この動画シリーズは
内容盛りだくさんですが、
無理に一気に頭に詰め込もうとせず、
自分に合ったペースで、ひとつずつ
確実に消化していってくださいね!
その10 ♭5を効果的に使う
解説はこちら
前回までは、
ブルースにジャズを混ぜる
という発想で解説してきました。
これでソロの雰囲気は、
かなりジャズ寄りになりました。
今回は逆に、ここから
ブルージーな雰囲気を強めるため、
ブルースの音使いで特徴となる
「ブルーノート」を混ぜていきます。
「ブルーノート」とは、
♭3、♭5、♭7の
音のこと。
このなかでも特に、
一番ブルージーな音は♭5ですので、
この音を積極的に使い、
ブルースの雰囲気を出していきます。
【♭5を効果的に使う】
■♭5の使いどころは??
ツーファイブで解決した直後の
B♭7 (Ⅰ7)のところで、
♭5の音を使います。
♭5は盛り上がりの音なので、
盛り上がりコードのところで
使うのが一番効果的…
といいたいところなのですが、
実は、
ブルース進行では全てのコードが
盛り上がりコードなのです。
■Fブルースのコード進行
|
F7
|
B♭7
|
F7
|
F7
|
|
B♭7
|
B♭7
|
F7
|
D7
|
|
Gm7
|
C7
|
F7
|
C7
|
「F7」は、ルート音からすると
落ち着きコードに見えます。
しかし、
よくよく伴奏を聞くと、
F7は少し濁った響きに
聞こえませんか?
F7の構成音には
メジャースケール外の音である
♭7が含まれています。
それが「濁り」を生んでいて、
このコードを盛り上がりコードに
変えているのです。
ですから、ここでは
盛り上がりの音である
♭5を使ってもOK!
なのです。
また、
ツーファイブのフレーズを弾くと、
どうしても「解決感」、
すとんと落ち着く感じが
出てしまいます。
ですから、次のコーラスで
盛り上がろうとする場合には
解決感をあえて薄めるために、
こんなふうにブルーノートを
落ち着きコードにぶつけたほうが
全体のストーリー展開が
スムーズにつながりやすいのですね。
動画の演奏を聴きながら、
また、自分で色々試しながら、
♭5の使い方をつかんでくださいね!
その11 2コーラスのアドリブストーリー展開
その12 3コーラスのアドリブストーリー展開
2本分まとめての解説はこちら
■ストーリー展開の
組み立て方
今回は、今まで解説してきた内容を
アドリブソロのストーリー展開に
落とし込んでいきます。
ずーっと同じテンション、
同じような音使いで弾き続けていると
聞いている観客も、
一緒に演奏しているメンバーも、
だんだんと飽きてきます。
ですから、
途中で雰囲気を変えたり、
盛り上げどころを作るなど
みんなを楽しませる展開を
意識して組むのが大切なのですね。
例えば、1コーラス目は
スケール一発にブルーノートを混ぜた
ブルース寄りの雰囲気から、
2コーラス目はアルペジオ中心で
ジャズの雰囲気に切り替えていく。
あるいは、
1コーラス目はアルペジオ中心、
2コーラス目からはスケール一発のソロ、
3コーラス目はブルーノートを
さらに増やして盛り上げていく。
そんなふうに、
「わかりやすく盛り上げる」
「わかりやすく展開をつける」
というのが、良いアドリブソロを
とるためのポイントです。
■コーラスの終盤では
『意思表示』が必要!
ジャズブルースの場合は、
12小節の1コーラスごとに
展開を変えていくのが
わかりやすい形です。
ですから、コーラスの終盤では
「次のコーラスは盛り上げます!」
という意思表示が必要です。
ここで、注意点がひとつ。
ジャズブルースの終盤で
ツーファイブのフレーズを入れるのは
「コードに沿ったソロ」なので
悪くはないのですが、
ツーファイブフレーズは、
演奏直後に「解決感」、
すとんと落ち着いた感じが
強く出てしまいます。
そのため、
次のコーラスへ向かって盛り上げる、
という意思は伝わりにくくなります。
そこで、前回解説したように、
ツーファイブフレーズの直後の
落ち着きコードで♭5を使う!
というようにすると、
解決感が薄まり、
次は盛り上げるという意思が
伝わりやすくなりますので、
非常にオススメです。
■まとめ。
全体のストーリー展開と
コーラス終盤での意思表示に
注意をしておけば、
コードに沿ってソロをとっても、
コードにとらわれずソロを弾いても
どちらでもOKです。
色々なパターンを試しながら、
自分にとってテッパンの
ストーリー展開を
見つけてみてくださいね!